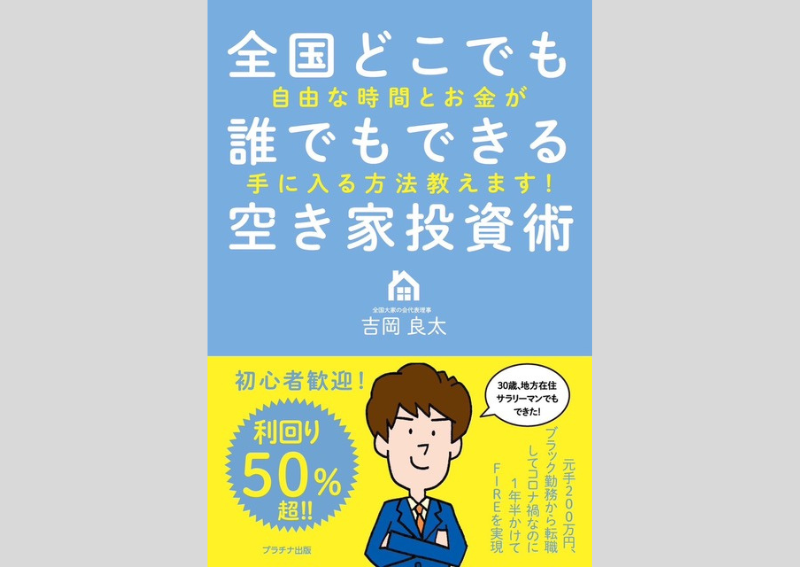事故物件の「告知」について国交省が案を発表 賃貸の3年は長いか短いか

2021/05/25

文/朝倉 継道 イメージ/©zens・photoAC
待ち望んでいた国交省のガイドライン
「事故物件」といえば、最近は多くの人が知る言葉となった。その事故物件に関連して、5月20日に国土交通省から重要なリリースが公表された。検討会がスタートした昨年2月以降、待ち望んでいたという人も業界には多いはずだ。
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」というタイトルになっている。
いわゆる事故物件に関して不動産業者がユーザーに対して行う告知の指針と単純にいってよいだろう。不動産において過去に人の死が生じた場合、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応と宅建業法上負うべき責務の解釈についてをとりまとめたガイドラインの「案」というかたちをとっている。
なお、本案については、21年5月20日から6月18日までの間、パブリック・コメントの対象として、広く国民への意見募集が行われている。募集要領などを載せたサイトへのリンクを下記に掲げておこう。
「電子政府の総合窓口(e-Gov)宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)に関する意見募集について」
対象となる不動産は
では、本案の内容のうち、要点となるいくつかを「賃貸物件」に関わる部分に区切って、ざっと紹介していきたい。まずは、本案が対象とする不動産の範囲だ。居住用賃貸物件に関しては、以下のとおりとなっている。
■借主の居住の用に供される専用部分
■借主が、日常生活において通常使用する必要があり、集合住宅内の当該箇所において借主に告げられるべき“事案”が生じていた場合において、借主の住み心地に影響を与えると考えられる部分
あとの方が若干ややこしいが、要は賃貸マンションやアパートの場合、ベランダ、廊下、階段、エントランス、エレベーターといった箇所がこれにあたる。さらに、このうち「借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分が(対象に)該当するものと考えられる」というのが、本案のスタンスだ。
これは、貸主(賃貸住宅オーナー)や、管理・仲介会社側にとっては、一応、息がしやすい指針といえるだろう。
例えば、殺人事件が、過去に物件5階の廊下で起こっていて、そのことをこれから1階の部屋に入居しようとする人に告げるか否かを考えるとすれば、多くのケースで、これを不要とする判断が可能と読み取ることができる。
なお、すでにお気付きの方もいると思われるが、上記の範囲には隣室など「他住戸」が入っていない。実は、これについてはいくつかの理由から、「今後(中略)適時にガイドラインへの採用を検討する」とし、そのため、「現時点において、これらの不動産を取引する際には、取引当事者の意向を踏まえつつ、適切に対処する必要がある」となっていて、今回は一旦棚上げされるかたちだ。
とはいえこの部分は、例えば、「ウチは事故があった部屋の隣室までは、入居希望者へ告知する」「いや、ウチは将来のクレームの元を断つため、建物全戸が対象だ」といったように管理会社・仲介会社などによって、さまざまに判断が分かれているのが現状だ。
そのため、本来ならば、ここでも何らかの提案が今回は待ち望まれていたともいえるだろう。しかし、それは以降ということで、この点、今後もしばらく現場の悩みは続きそうだ。
次ページ ▶︎ | 事故物件…どこまで申告する必要があるのか
事故物件…どこまで申告する必要があるのか
次に、「告げるべき事案」の範囲を見てみたい。
「他殺」「自死(自殺)」「事故死」「原因が明らかでない死」が原則として借主にこれを告げる対象となっている。一方、老衰、病死など、いわゆる「自然死」は原則対象とされていない。
なおかつ、事故死についても、階段からの転落や、入浴中の転倒といった、日常生活のなかで生じた不慮の事故によるものに関しては、やはり「原則としてこれを告げる必要はない」とされている。
そのうえで、自然死や不慮の事故死であっても、「長期にわたって遺体が放置されたことなどにより、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合」においては、話が別となる。これらは、原則告げるべき事案、すなわち告知の対象となるかたちだ。
以上、告知対象の事案別の切り分けについては、多くの立場で、納得しやすい提案がされているといえるのではないか。
加えて現状、賃貸住宅の入居者におけるあらゆるかたちの死について、これを一律に告知の対象にすべきとする一部の考え方が、単身高齢者の入居機会を狭める方向に波及しているとされる問題についても、上記は、それに対する処方箋のひとつになりうるものといえるだろう。
報告義務は3年…これは短い? それとも長い?
次に、ここは今回一番のポイントといえるかもしれない部分だ。
よく話題となる、「事故物件であることの告知をいつまで続ければよいか」について、本案は、具体的な年数を挙げての提案をやや踏み込んだかたちで行っている。その年数とは「概ね3年」だ。
■告げるべき事案が発生している場合
■これを認識している宅地建物取引業者は
■事案の発生から概ね3年間は、借主に対してこれを告げるものとする
と、なっている。なお、どこが踏み込んだ部分かといえば、それは、事案発生後の入居者の入れ替わりの実績をここでは排除している点にある。
時折ウワサされるところの、事故物件に短期間だけ人を頼んで住まわせ、当該人物に早期退去してもらったのちに告知をやめるような「作戦」を選べなくさせる意図が、ここには多少感じられるところだ。
ただし、一方で3年という期間は、一般目線からは短いと感じられる可能性も高いだろう。そこで人が自殺したり、殺されたりしたのならば、4年、5年、あるいは将来限りない期間にわたって告知してほしいと感じる入居希望者も、世の中には少なくないのに違いない。
しかしながら現状として、そうしたニーズに対しては、不完全ながら半ばインフラ化したツールとしての「事故物件サイト」もすでに存在する。
そうした“民間努力”も見据えたうえでの3年であり、さらには、貸主と管理・仲介会社が現状背負う、重い肩の荷を下ろしてやるための3年ということであれば、この数字は、まずまず妥当なものといえるのではないだろうか。
以上、今回の国交省のリリースの概要については下記リンク先にて確認されたい。「案」本体を直接ご覧いただくには、前掲のリンク先の方が便利だろう。
「国交省 宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します」
なお、今回の「案」にもとづき、実際にガイドラインが成立した場合でも、これに強制力があるわけではない。
しかしながら紛争時など、宅建業者に対し行政庁が監督・指導を行うにあたっては、(成立後の)本ガイドラインの内容が考慮されることとなる。民間のみでは長年コンセンサスをつくれずにいた案件について、行政がそれを一旦固めるという意味において、今回の国交省の仕事は、世の中が渇望していたものといっていいだろう。
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。